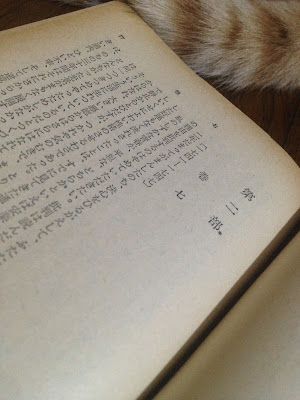新井紀子『AI VS.教科書が読めない子どもたち』が面白かった。
例えば、AIは以下の二文の(構造的な)意味の違いが読み取れない。
また、AIには以下の二文が同義であるかどうかの判定が難しい。
ちなみに、次の( )を埋めるような問題は逆にAIは得意である。
こういう場合AIは、「幕府」「ポルトガル人」「追放」「大名」「沿岸」「警備」で検索をかけて、合致度の高い例文を特定し、その文中にある「〇〇年」という該当部分を見つけ出してくるというやり方をする。この場合、助詞や態は無視しても問題ない。
こういった、文章をぶつ切りにして名詞要素を検索キーとして取り扱うだけの「表層的読解(意味理解を伴わない読解)」でも、AIの記憶力と計算力(総当たり的比較力)を持ってすれば8割ぐらいの現役受験生より入試で点が取れてしまう(東大は無理だけど学部学科を選べばMARCH関関同立に合格できるレベル)というのだから、なかなか衝撃的である。
AIは、文章全体の意味を読み取るみたいなこととは全く異なることをやっている。のだけど実は、そもそも人間が文章を読んで意味を理解するということがどういうことなのかは、まだ解明されていない。だからそれを数学的モデルとして取り扱うことなんて夢のまた夢で、今は単に工学的な力技で片っ端から例文と比較して重み付けでやるしかないし、せいぜいその効率的な比較法を開発するか、例文の量を増やして「精度を上げて」いる。
ここから導かれることとして本書は、人間が手に入れる読解力として表層的読解がいくらできても、いずれAIに取って代わられるだろうと予測する。だから、AIが苦手とする「深い読解」 の方に希望があるのだけど、どうやら人間(中高生)もAIと同様の傾向があることが調査でわかってきた。AIが得意なタイプの読解はできるけど、AIが苦手なタイプの読解ができていない。
中高生しか調査してないので「子どもが」「読めない」という話になるけれど、教育方法は大きくは変わっていないので、現状の大人も当然そうだろうと。
もっとも(これは書いてないけど)ある程度以上の高齢世代であれば、AIの進歩速度に対して逃げ切れるだろう。だからいずれにせよ、注力するとしたら若年世代ということになると思う。
終盤。
AIが得意な読解も苦手な読解も含んだ基礎読解力(中学の教科書程度の文を読み取れる力)を養うために、著者は、「処方箋は簡単ではない」がと前置きし、
と書いている。
自ら検証したことをもとに大胆かつ明確に断言していくこの著者の文体にしては、この部分だけ、非常に控えめな表現になっている。「予感めいたものを感じています」。
確かに証拠を挙げにくいことではあるのだけど、この「精読、深読になんらかのヒント」あたりについて、僕たちがここ何年かやっている、読む・書く・残す探求ゼミや講読ゼミと、かなり関連があるのではないかと思う。なぜならここを僕たちは何度も確かめてきた。
書かれているものを、予め自分が持ってしまっている言語ネットワークに当てはめるように読むのではなく、読み進めることで自分の言語ネットワーク自体を動的に変化させていくような読み方。
力の比喩で言えば、
簡単に腑に落としてしまわないで、書かれたそのままを保ち続ける(保留する)筋力。
こういった、一般に「理解」と言われているものとはニュアンスの異なる状態が、〈読解〉に、〈理解〉に、〈意味〉にむしろ深く関わっているのではないかと思っている。
こういうあたりのことを僕はこれからもやっていきたいし、せめてもう少しうまく言えるようになりたい。
例えば、AIは以下の二文の(構造的な)意味の違いが読み取れない。
・先日、岡山と広島に行ってきた。また、
・先日、岡田と広島に行ってきた。
(169頁)
・警報機は絶対に分解や改造をしないでください。の構造的な違いが読み取れない。ということは、たぶん、
・未成年者は絶対に飲酒や喫煙をしないでください。
(125頁)
・ファッションモデルは太らない。の違いも読み取れないだろう。
・こんにゃくは太らない。
また、AIには以下の二文が同義であるかどうかの判定が難しい。
・幕府は、1639年、ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた。同じ名詞がほぼ同じように並んでいるからほぼ同じ意味の文ということになってしまうようだ。助詞や受動態は無視しているのだろう。
・1639年、ポルトガル人は追放され、幕府は大名から沿岸の警備を命じられた。
(205頁)
ちなみに、次の( )を埋めるような問題は逆にAIは得意である。
・幕府は、( )年、ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた。
こういう場合AIは、「幕府」「ポルトガル人」「追放」「大名」「沿岸」「警備」で検索をかけて、合致度の高い例文を特定し、その文中にある「〇〇年」という該当部分を見つけ出してくるというやり方をする。この場合、助詞や態は無視しても問題ない。
こういった、文章をぶつ切りにして名詞要素を検索キーとして取り扱うだけの「表層的読解(意味理解を伴わない読解)」でも、AIの記憶力と計算力(総当たり的比較力)を持ってすれば8割ぐらいの現役受験生より入試で点が取れてしまう(東大は無理だけど学部学科を選べばMARCH関関同立に合格できるレベル)というのだから、なかなか衝撃的である。
AIは、文章全体の意味を読み取るみたいなこととは全く異なることをやっている。のだけど実は、そもそも人間が文章を読んで意味を理解するということがどういうことなのかは、まだ解明されていない。だからそれを数学的モデルとして取り扱うことなんて夢のまた夢で、今は単に工学的な力技で片っ端から例文と比較して重み付けでやるしかないし、せいぜいその効率的な比較法を開発するか、例文の量を増やして「精度を上げて」いる。
ここから導かれることとして本書は、人間が手に入れる読解力として表層的読解がいくらできても、いずれAIに取って代わられるだろうと予測する。だから、AIが苦手とする「深い読解」 の方に希望があるのだけど、どうやら人間(中高生)もAIと同様の傾向があることが調査でわかってきた。AIが得意なタイプの読解はできるけど、AIが苦手なタイプの読解ができていない。
中高生しか調査してないので「子どもが」「読めない」という話になるけれど、教育方法は大きくは変わっていないので、現状の大人も当然そうだろうと。
もっとも(これは書いてないけど)ある程度以上の高齢世代であれば、AIの進歩速度に対して逃げ切れるだろう。だからいずれにせよ、注力するとしたら若年世代ということになると思う。
終盤。
AIが得意な読解も苦手な読解も含んだ基礎読解力(中学の教科書程度の文を読み取れる力)を養うために、著者は、「処方箋は簡単ではない」がと前置きし、
もしかすると、多読ではなく、精読、深読に、なんらかのヒントがあるのかも。そんな予感めいたものを感じています(246頁)
と書いている。
自ら検証したことをもとに大胆かつ明確に断言していくこの著者の文体にしては、この部分だけ、非常に控えめな表現になっている。「予感めいたものを感じています」。
確かに証拠を挙げにくいことではあるのだけど、この「精読、深読になんらかのヒント」あたりについて、僕たちがここ何年かやっている、読む・書く・残す探求ゼミや講読ゼミと、かなり関連があるのではないかと思う。なぜならここを僕たちは何度も確かめてきた。
書かれているものを、予め自分が持ってしまっている言語ネットワークに当てはめるように読むのではなく、読み進めることで自分の言語ネットワーク自体を動的に変化させていくような読み方。
力の比喩で言えば、
簡単に腑に落としてしまわないで、書かれたそのままを保ち続ける(保留する)筋力。
こういった、一般に「理解」と言われているものとはニュアンスの異なる状態が、〈読解〉に、〈理解〉に、〈意味〉にむしろ深く関わっているのではないかと思っている。
こういうあたりのことを僕はこれからもやっていきたいし、せめてもう少しうまく言えるようになりたい。